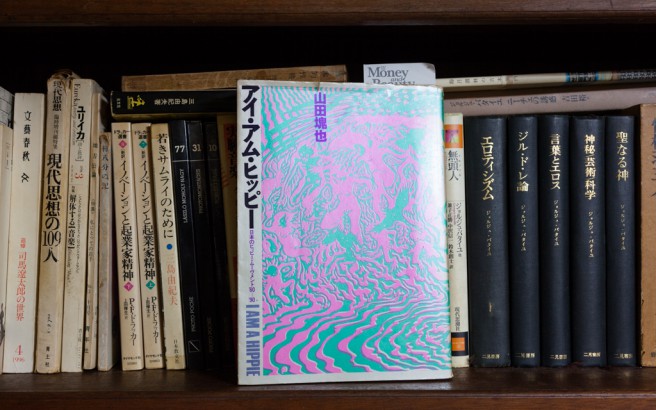タテバ?古紙屋さんの大元締めっさ。いわゆるちり紙交換の元締めさ。紙のゴミばみんな持って来るとよ。そこばタテバ言うとった。もー山んごと本ば積んであっさ。ゴミよ、ゴミ。そいけんそんな中で、まー汚れ仕事さ。ゴミん中で漁りようごとあって、あんまよか仕事じゃなかとさ。そいけん嫌うとこも多かったとよ。はーそいでも、やっぱ凄いのもあったけんねー、四十年代五十年代は。あん頃は家ば崩したり建て替えたり、丁度そんな時代やった。そいけんタテバば巡って、本ば集めて、どんどん東京に送ったとよ。
これは今年の三月に長崎に取材旅行に行ったとき、老舗の大正堂さんから聞いた話だ。テープから直接おこしたので長崎弁もそのままにしてある。建場(『タテバ』と読む)についてアレコレ言うより、直接行っていた人の言葉をそのまま載せたほうが信憑性がある。
わたしが建場という言葉を初めて聞いたのは、数年前、これも古書通信の取材で岩手に行ったときだ。そこで老舗の古書店さん(確か東光書店さんだった)を取材した時、もう八十近い店主さんが建場の話をされた。内容は大正堂さんと同じで、建場を巡って、いい本をたくさん集めて、東京にバンバン送ったというもの。
建場。大正堂さんの言葉にあるように、要は古紙回収業の元締め。ゴミの倉庫である。いろんな古書店さんから聞いた話を総合すると、八十年代頃までは、建場は古書店の主要な仕入れ先として、日本全国で機能していたようだ。今はどうか知らないが、昔は相当凄かったらしい。建場で見つけたお宝を、神田の市場に送ったらウン百万になった的な話は、地方の老舗古書店を取材すれば必ず出てくる。
建場。わたしはまだ行ったことはないが、なんとも興味を引かれる場所である。
古本屋は、誰かが不要になった本を、他のそれを必要としている人のもとに届ける、そういう仕事である。不要ではあるが、まだゴミではない。だけれども、そうしたリサイクル業者としての古本屋の機能を一歩進めれば、廃棄されたゴミの山(建場)からお宝を漁る、というのもアリっちゃーアリである。でもそうなると、ゴミ箱を漁るホームレスさんと、古本屋は、たいして違いがないことになってしまう(笑)恐ろしい。でも、行ってみたい・・・。

話は変わるが、建場とともに、わたしの中で一種神秘化された存在として、セドリ師がある。セドリ師に関しては、少し前にネットでセドリに関するマニュアルや講習会などが盛んに宣伝されていたので、知る人も多いだろう。彼らはブックオフの100円コーナーなどで本をセドり、Amazonなどで売って利ざやを稼ぐ人だ。だがわたしの言うセドリ師は、彼らニューカマーとは別である。
これまた古書通信の取材で地方に行くと、八十年代より前は、リアルに古書業界でセドリ師なるものが暗躍(?)していたことが分かる。
今は古本が猛烈な値崩れを起こしているし、ネットの価格が日本全国隅々にまで浸透しているので、地方と東京の古書価の差は無いに等しい(むしろ今は東京の方が安かったりする)。だが、物の流通が今ほど低価格で整備されておらず、またインターネットも存在しなかった八十年代より前は、地方と東京の古書の値段は、最低でも二割程度の差があったそうだ。だからそれほどのお宝でなくても、大量に地方でセドって中央に持ってくるだけで、セドリ師は利ざやを稼げた。また、建場も機能していたので、実際に地方で掘り出し物に出くわす機会も多かった。そんな訳で、地方の古書店を取材すると、昔はお店や地元の古書催事などに、神保町の大店が雇ったセドリ師が頻繁に来ていた話がよく出る。そんな時わたしは、そのセドリ師がどんな風貌だったか。目つきは鋭かったか。無口だったか快活だったかと、しつこく尋ねるのだ(笑)
わたしがセドリ師を初めて知ったのは、つげ義春の漫画『無能の人』の中でだ。その中で、主人公の友人の半病人のような古書店主が、もとはセドリ師という設定だった。その頃からセドリ師はわたしの中で神秘化され、会ってみたい人ナンバーワンになった。実際に古書通信の編集長の樽見氏に、セドリ師を知りませんかと聞いたことがある。すでに引退しててもいいから、昔のセドリ師に会って取材してみたかったからだ。その希望はいまでもある。
以上、わたしが古書通信の取材をしてきた中で見聞した、古書業界の深部ともいうべきセドリ師、ハタ師、建場、初出し屋について、思うつくままに書いた。ハタ師に関しては、シルバーゼラチンさんを取材することで出会いが実現し、初出し屋の存在も確認できたが、建場とセドリ師に関しては取材は実現していない。
古書業界はいま、大きな変革のなかにある。もはや古書店という存在自体が社会のブラックボックスと化し、たとえ業界が今後続くとしても、昭和以前の在り方は姿を消していくだろう。セドリ師、ハタ師、建場、初出し屋といった前近代的な古物界の業者や場も、サンカやマタギのように消えていくに違いない。時代の変化といえばそれまでだが、わたしのような古き良き古書店を愛する者にとっては、ちょっと寂しい限りである。
とはいえ、この世にモノが溢れる限り、古書店のようなリサイクル業がなくなることはない。今後もいろんなお店を取材しながら、これからの古書店像を探っていきたい。
なんて無理矢理思っても無いことを書いて、忙しいのでこの文章を締めさせていただきます。(おわり)